
さて今回は犬のトレーナーになりたい人の活動先の一つ、補助犬トレーナーについてお話ししていきたいと思います。
ちなみに補助犬(正式名称:身体障害者補助犬)とは以下3種のことを指します。
- 盲導犬・・目が見えない、見えにくい方のお手伝いをする犬
- 介助犬・・手や足に障がいがあり、車椅子に乗っている方等のお手伝いをする犬
- 聴導犬・・耳が聞こえない、聞こえにくい方に音を知らせるお手伝いをする犬
みなさんは「補助犬」と聞いてどんなイメージがあるでしょうか?
私も専門学校の在学中に先生から聞かれたことがあります。その時は厳しい訓練をしている、働かされている犬、という印象が強くそのようにお話しした記憶があります。ですが、実際に施設に出向いたり話を聞いてみるとそうでもなく、むしろとってもハッピーな犬ばかりでした(団体により大きく異なりますが、、)
今回はドッグトレーナーを目指す、目指したいと思っているみなさんに、補助犬トレーナーについてお話ししていきたいと思います。是非最後までお付き合いくださいませ🐾
働く犬、補助犬とは

先ずは補助犬について正しく理解していきましょう。
みなさんは働く犬、と聞いてどのような犬が思いつくでしょうか。いくつか挙げてみましょう
- 警察犬
- 災害救助犬
- 麻薬探知犬
- セラピードッグ などなど
世の中ではもっとたくさんの犬が働いてくれています。
そんな働く犬の中で身体に障がいのある方のお手伝いをする犬のことを”補助犬”と呼びます。
目が不自由な方を手伝う「盲導犬」
耳が不自由な方を手伝う「聴導犬」
手や足が不自由な方を手伝う「介助犬」
では一つずつ見ていきましょう!
身体障害者補助犬(通称:補助犬)とは盲導犬・介助犬・聴導犬の3種の総称です
盲導犬とは
補助犬の中でみなさんが一番聞き馴染みの多く、歴史的にも実働数的にも一番多いのが「盲導犬」です。
盲導犬とは、目が見えない・見えにくい方に「障害物」「段差」「曲がり角」などを教えてくれます。
私も勘違いしていたのですが、盲導犬の対象者は全盲(全く目が見えない人)だけでなく、視野が狭くなる視野狭窄、まわりが光って見える透光体混濁などの方も対象となります。
あとよく勘違いされるものとしては、盲導犬はナビではありません。「スーパーまで」と言っても分かりません。どうしてるのかというと、盲導犬使用者さんの頭の中に地図があり2番目の曲がり角を左、そのまま横断歩道を渡って、次の交差点で右、などを覚えて盲導犬に指示を出しています。
そして犬は色の識別ができませんので、信号機の色も分かりません。目が見えていない方がどう渡っているのか、それは雰囲気だそうです。音で聞いていけるかな、と。
是非街中で困っている人をみかけたら、勇気を出してお声掛けください。
電車のホームでの盲導犬使用者の転落事故もまだ記憶に新しい方もいるのではないでしょうか?もちろん当時話題になったホームドアの設置ができれば一番ですが、費用もかかりますし何しろ今すぐに設置できるものでもありません。では、どうすれば、
それは優しい声掛けだと私は思います。手間も費用もかからずできますよね?
街中でも電車内でも携帯を触っている人、イヤホンをつけている人が大半で周りを見ていない人も多いのではないでしょうか?歩きスマホで視覚障害者とぶつかってこけたという話も聞いたことがあります。
周りを見て、困っている人には優しい声かけが普通にできる世の中になれば、と心底思う筆者です。
介助犬とは
続いて介助犬。ご存知ない方も多いのではないでしょうか?
介助犬とは病気や事故などで手や足に障がい(以下、肢体不自由者)を負い、車椅子に乗っていたり杖をついて歩いている人のお手伝いをします。
具体的にいうと、肢体不自由者は腹筋や背筋の筋力低下や体幹機能が低下している人が多いので落とした家の鍵やお金なんかも拾ってくれます。そのほかにも冷蔵庫から飲み物をとりにいってくれたり、緊急事態の備えて携帯電話を探して持ってきてくれたりするそうです。
こちらもよく勘違いされること、それは「介護」犬です。これから高齢者社会だからますます重要ね、と思われる方も多いそう。
車椅子に乗っている人は必ずご高齢の方だけでなく小さなお子さんも乗っていることもあるでしょう。介助犬は若くして障害を負った方が介助犬と共にもう一度社会参加したい自立したいという方のサポートをしてくれます。
また一概に肢体不自由者といっても障害はさまざま。杖をついて少しは歩ける方もいますし、車椅子の種類にも手動・電動・大型電動など異なります。その方一人一人に合わせたオーダーメイド性が必要なのが他の補助犬と違うところになります。
また、肢体不自由者の身体の可動域や負担になる動きは専門家にしか分かりません。リハビリテーション科の医師や作業療法士、理学療法士などなどたくさんの方とチームを組んで取り組む必要があるんだそうです。
聴導犬とは
聴導犬も介助犬と同様あまり聞き馴染みがないかもしれませんね。
聴導犬は耳が聞こえない、聞こえにくい人に音を知らせ、音源まで誘導をする、お手伝いをしています。
どのように音を知らせるのかというと、もちろん耳が聞こえないので吠えても分かりません。なので鼻や前足なのでツンツンと音鳴ってるよ、と教えてくれます。その後音源まで、たとえばお湯が沸騰している音ならキッチンまで、インターホンがなったらそこまで誘導してくれます。
あと重要なお仕事は緊急時!!火災報知器の発動時も音が聞こえません。そんな緊急時にはその場で伏せをして教えてくれます。聴覚障害は他の障がいと違い周りからは分かりにくいです。緊急時には全員がパニックですから取り残される危険性もあります。そんな時にも聴導犬が教えてくれます。
あと少し前文でも触れていますが、聴覚障害は周りから気付かれにくいです。ですので、クラクションの音や、自転車のチャリンチャリンの音も聞こえないので、怒られた経験をされた方も多いそう。そして気をつけるがあまりに外出をしたくない、少し出かけるだけですぐに疲れるという方も多いそうです。ですが、盲導犬や介助犬もですが「聴導犬」と書かれたケープを犬が着ているので、周りに気付いてもらえるようになった、という効果もあるそうです。
厳しいトレーニングしてるってホント?

一昔前は厳しい訓練をしているところも多かったのが事実のようですが、今は楽しくトレーニングをしている団体も多くなりました。ですが、本当に団体によって異なります。自分で興味のある団体を調べてみると良いでしょう。HPをみると団体の活動がわかると思いますし、実際に足を運ぶと差は歴然です。
私も専門学校在学中に盲導犬協会2団体と介助犬協会1団体に調べた上で見学に行きましたが全然違います。調べてから実際に行っても良い意味でも悪い意味でも違いますよ笑
団体数だけでいうとたくさんありますが、本当に活動してるの?という団体があるのも事実のようです。
前述した通り、自分で調べ足を運んで様々な団体をみると良いでしょう。運命の巡り合わせがあるかもしれませんよ。
どうすれば補助犬トレーナーになれるの?
ドッグトレーナーと同じで資格制度はありません。変なはなし私補助犬トレーナーです、と言えてしまうのが現状です。
ただ殆どの補助犬団体が各自の制度、盲導犬訓練士学校や研修生といった制度などを取り入れています。募集は毎年ないことも多く、あったとしても倍率は高く狭き門となっています。気になった団体はHPやSNSをこまめにチェックしておくとよいでしょう。
そして補助犬、と聞くと犬のトレーニングするのがお仕事、と思われている方も多いです。もちろん犬のトレーニングは必要で覚える必要もあるでしょう。ですが、同等に障がいのことを学ぶ必要があります。視覚障害者、肢体不自由者、聴覚障害者のことが分からず働くことは無理に等しいでしょう。犬だけでなく福祉についても広く学ぶことが必要です。
なので、補助犬団体で働く人は動物系の専門学校から卒業して進む人、福祉関係の大学に進学後に進む人など経歴はまちまちのようです。
犬のトレーニングだけしたいという人は向いていないのかもしれません。逆に福祉にも興味がある、犬と共に人の役にたつ仕事がしたい、犬を介して人を幸せにしたい、と思っている方は向いているのかもしれませんね。
収入は?
補助犬団体のほとんどは寄付で活動されています。もちろんお給料もその中から支給されます。なのでかなり少ないと思います。(団体によって差はあると思いますが)
お給料よりもやりがいを求める人なら良いのかもしれませんが、平均的な給料を目指すなら難しいでしょう。
まとめ

いかがでしたでしょうか?
身体に障がいのある方のお手伝いをする「補助犬」その子達を育成しているトレーナーの活動について今回はご紹介しました。
まだ動物の専門学校進学を迷っている方は補助犬団体と繋がりがあるか聞いてみるのも良いでしょう。なかなか見学やインターンをしている団体は少ないものの繋がりがあれば引き受けてくれる可能性もありますよ。
今日はここまでっ🐾
最後までご覧いただきありがとうございました〜!!

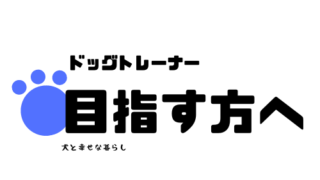
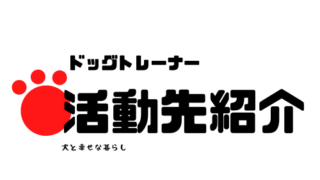





コメント